国立新美術館のお仕事探訪 ~インターンが聞く!バックヤードインタビュー~ Vol. 1 学芸課:企画室編
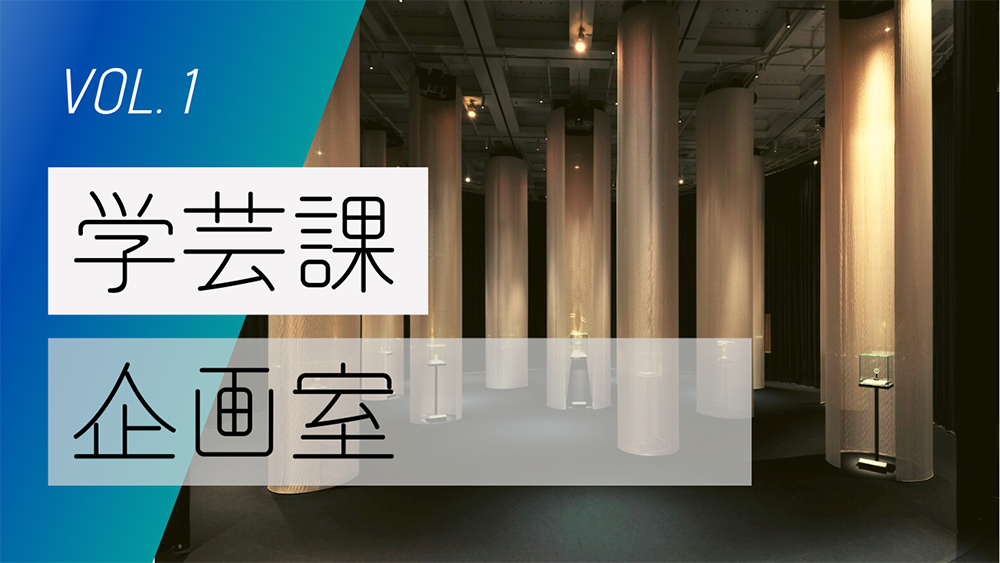
インタビュイー:本橋弥生主任研究員
- ≪本橋研究員が担当した展覧会≫
- 「ファッション イン ジャパン 1945-2020―流行と社会」(2020年)、
「カルティエ、時の結晶」(2019年)、
「ウィーン・モダン クリムト、シーレ 世紀末への道」(2019年)、
「ミュシャ展」(2017年)、
「MIYAKE ISSEY展:三宅一生の仕事」(2016年)、他。
本橋さんの普段の業務内容を教えてください!
私は国立新美術館(以下、新美)が「ナショナル・ギャラリー」という仮称だった頃に採用され、開館前の準備段階から20年近くここにいます。それまではずっと学生だったので、ここが最初の職場です。今は企画室で展覧会の仕事が中心ですが、最初は教育普及室に在籍しており、展覧会と教育普及事業の両方を担当していました。
展覧会は大体3年~5年、長い時には下手をすれば10年近くのスパンで動くこともあるので、普段から「こういった展覧会がやりたいな」というアイデアをいくつも貯めておくようにしています。そのストックの中から、時代に合ったものや、開催資金の目処が立ちそうな企画を館内の会議に持ち寄り、了承してもらえると本格的に進める流れです。会議に出す段階で、大体6~7割程度構想ができていないと、実現が難しいですね。新聞社などに共催をお願いしたり、サポートや物資提供などの協力を募ったりするのと同時に、企画の内容をもっと掘り下げるためにリサーチする、といったことをやっています。
海外の美術館だと、5年に1度程度の大きな展覧会をやるために、キュレーターやリサーチアシスタントからインターンまで、最終的には総勢100人くらいという体制で展覧会を作るところもありますが、日本は残念ながら資金的にも人材的にもそのような恵まれた環境になく、分業もされていません。なので、場合によっては、企業の協力をとったりするところから関連イベントまで、展覧会担当を中心に企画して運営している感じです。
新美の学芸員の中でも、何に興味があるとか、このあたりが専門、というようなゆるやかな分担があります。フランスの美術、ドイツの美術、現代美術、マンガやアニメ......となんとなく分かれていて、私はデザインやファッション、建築、美術でも主流ではなく東欧や北欧といったマイナーでニッチなところを担当しています。
新美は所蔵品がなく、「さまざまな美術表現を紹介し、新たな視点を提起する美術館」というのが活動方針の一つとなっています。越境するというか枠を超えるというか。いろいろな既成概念を越えて新しい関係性を生み出す――そんな活動ができるといいなと思っています。とはいえ、本当は100人くらいスタッフがいたら海外の美術館みたいにできるのですが、理想には程遠いのが現状です。でもだからこそ、インターンさんも含めて何か新しいプロジェクトなどをしていけたら、ライブ感のある、新しいものが生み出されていくような美術館になるんじゃないかなと思っています。

展示や関連イベントの企画は、お一人で行っているのですか?
大体メイン担当とサブ担当の2~3人のチームになって作ることが多いです。私の場合は、現在活躍する作家さんの活動を紹介することが多いので、その方のことを深く理解していくうちに、「これをみんなに聞かせてあげたい!」と思うことが増えてきます。なので、関連イベントの案も、リサーチの過程で沢山湧いてきます。作品について知っているつもりでも、作家さんから直接お話を聞いたり、作品に近い時代の方からお話を聞くと、新しい発見がたくさんありますし、違う角度から作品を見ることもできるんです。いろいろな人に「こんな企画だから協力してください」「これについて教えてください」とお願いしているうちに、どんどん深まっていくのが醍醐味というか、この仕事をやっていて一番楽しいところだと感じています。
学生時代の専攻や研究の内容を教えていただきたいです!
私は典型的な学芸員の道を辿っていないので、皆さんのお役に立たないような気がするのですが(笑)。修士課程は文学部の美術史専攻でしたが、美術史のなかでもマイナーな、東欧(ハンガリー)と北欧(フィンランド)美術を選びました。ほぼ美術史の中でも研究されていないところです。子どもの頃から、あまり知られていないヨーロッパの秘境のようなところに行ってみたいという気持ちが強くて。ちょうど高校生の時にベルリンの壁が崩壊して、東欧に行けるようになったんですね。それでハンガリーのブダペストに行ってみたいなと思っていたんです。中欧の真ん中にあるのにアジア系の言語を使っていて、「ヨーロッパの中のアジア人」などと言われたりしているのを聞いて、いつか行ってみたいなと思っていました。
そんな訳でハンガリー美術を研究することになり、最初はハンガリーでも国際ゴシックを調べようと留学したのですが、ブダペストの街並みがなんだかかわいいんですよ。アールヌーヴォーの街並みなのですが、ただ単にフランスのアールヌーヴォーを受容したものではなくて。ハンガリー建築が19世紀末から20世紀初頭にかけて模索され、ブタペストの街並みができたことに興味を持つようになりました。そのことをまとめた方が面白いし資料もたくさんあるので、修士論文は「ハンガリーのナショナリズムと建築」をテーマに研究したんです。
ハンガリーに留学中、周りには大勢のフィンランド人がいました。フィンランド語もアジア系の言語なんですね。フィンランドはロシア、ハンガリーはオーストリアから独立しようとする運動が19世紀末から20世紀初頭に高まって、言葉も似ているし連携が強化され、友好関係を築いてきたんです。その交流が100年以上経った今も残っていて、ハンガリーには大勢のフィンランド人が留学しています。そんな彼らと意気投合したことがきっかけとなり、博士課程ではフィンランドのヘルシンキ大学に留学しました。
フィンランドでは、建築家のエリエル・サーリネンやアルヴァ・アアルトが有名ですが、実はサーリネンとハンガリーの建築家やアーティストたちとの間に交流があったんですね。採用はされませんでしたが、サーリネンがブダペストの都市計画案を立てていたりだとか、そんなことも面白いなと思って調べているうちに30歳が目前に迫る年齢になっていました。就職しなきゃなと思って帰国し、採用してもらえたのがこの新美で、今、ここにいます。 新美のような、所蔵品がなくて、あえて新しいところに挑戦することを掲げている美術館だから、運よく私は採用してもらえたと思うのですが、美術館の立場からすると、やはり収蔵作品に近い専門家が欲しいですよね。なので、本当に学芸員を目指される方は、私のように変わった専門分野を選ぶのは、正直なところあまりおすすめしません(笑)。
就職したときに博士課程を一度は中退したのですが、今度はファッションをテーマに調べてみたいという気持ちが強くなり、再び博士課程に入りました。美術史ではなく、社会学研究科で学んでいます。なかなか個人的に研究する時間が取れず、在学年限がギリギリという状況で、論文が書けるのかという状況ですが......。というのも、次の「ファッション イン ジャパン1945-2020―流行と社会」展とも重なるのですが、洋装化以降の20世紀の日本のファッションの歴史に大変興味があり、ずっと調べてみたいと思っていたんです。
日本のファッションといえば、1970年代の日本人デザイナーが世界で活躍するところを起点にしているという見方が現在は主流ですが、その前に何があったのか、そして、なぜ敗戦した1945年から25年間という短い期間で、1970年代に世界で活躍する素晴らしいデザイナーたちが登場したのかということを、知りたい、掘り下げたいというのがあり、それが「ファッション イン ジャパン1945-2020 流行と社会」展構想の原点にあります。現在のファッションの状況をきちんと理解するためにも、洋装が一般化した戦後から現在までの装いと流行、社会の歴史をきちんと研究していきたいと思っています。

先程のお話にも出てきましたが、やりがいのある仕事や、印象に残っている仕事はありますか?
自分が一番やりがいを感じると思う瞬間は、人にあまり知られていなかったもの、人々から忘れられていたものを発見して、それを伝えた時に、観る方に喜んでもらえた時です。学芸員は雑用員って言われますけど、確かに楽な仕事ではないので、来場者の中に一人でも共感してくださる方、喜んでくださる方がいらっしゃれば、本当に嬉しいです。
研究とは違って、展覧会は一人でできるものではないので、大勢の方との協働で創り上げていくものです。一人一人立場も違ければ仕事の内容も違うし、海外の人とのやりとりもすごく多いので、素敵な人に出会ったりするとものすごく楽しいし、幸せです。普通の生活では出会うことのできない人と一緒に仕事をできることもあります。尊敬する人に出会い、自分も少しでもこのようになれると良いなと思ったりして......そういうのはすごく幸せな瞬間ですね。
今までに出会った方のなかで、特に印象に残った方はいらっしゃいますか?
皆さん、本当に印象深い方々ばかりです。最近では、安藤忠雄さんが強く印象に残っています。作品が素晴らしいのはもちろんですが、お人柄というか熱意がもう桁違いなんです。会期中、大阪からご来館してくださり、ご自身の言葉で伝えたいと週3回ギャラリートークをなさったんです。一日3回、週に9回くらい。お話もすごく面白いので、毎回会場いっぱい、200人くらい集まるんです。トークの内容も原稿を読むとかじゃないんですよ。毎回違うんです。著名なゲストも参加されたりもしました。静かに作品を観る展覧会の会場とは思えないほど、すごい熱気に包まれたのは忘れられません。
トークの最後に、来場者の方々と対話しながら図録にサインされていたのも、すごいなと思いました。それは一生の宝物になりますし、新しい創造力の種が蒔かれていることでもありますよね。一分一秒を無駄にしないようにと、打ち合わせの空き時間にもサインをなさっていたのには感動しました。

美術館で働くことになった動機を改めて教えていただけますか?
高校時代をイギリスで過ごしていたんですが、それまではずっと日本で教育を受けてきたので英語ができなくて。その時にアピールできることといえば、非言語的な科目のアートと体育で、すごく評価してもらったんですね。アートの授業は、こんなふうに作品を作りましょう、こんな風に見ましょうとかいうことではなくて、自分で好きにテーマを決めてポートフォリオを作って、調べて、描いて、表現していくというものでした。向こうの教育って褒めることで人を育てるので、アートでいっぱい褒められたんです。
ロンドンにいたのですが、当時は日曜日はお店は閉まり街が閑散としているのですが、美術館は開いていたんですね。他に出かける選択肢がないのと、すっかりアート好きになっていたのとで、毎週日曜日にロンドンの美術館を回っていたんです。最初は、「かっこいいな」とか「こんな表現あるんだ」とかそんな感じで見ていたのですが、そのうち展覧会のテーマとか切り口とか、「こういう見せ方もあるんだ」というキュレーションに目が行くようになって。
大学で日本に帰ってきた時は、日本語で勉強できるのが嬉しくて、最初はフランス文学を専攻したんですけど、結局やっぱり自分が好きなのは美術かなと思いました。ただもう自分が制作ではない方を選んでいたので、美術史を研究する方を選んだんです。
たまたま開館準備を始めるところだった「ナショナル・ギャラリー」(新美の仮称)というのがあって、こういう間口が広そうな新しい美術館であれば採用してもらえるかしらと受けてみた感じです。採用してもらえて本当に良かったです。
今後やってみたい企画を教えていただけますか?
新美は学芸員が企画展を担当する展示室が2つあることに加え、職員が少ないので、一人の職員が担当する展覧会の回数が多いんですね。一年に一~二本を担当することが多いのですが、毎回新しいことをやりたくてしょうがなくなっちゃうんですよ。あとで後悔するんですけど(笑)。展覧会は大勢の人と作り上げているから、苦しいことも多いのですが、すごく達成感があって、頑張っちゃうんですよね。「ウィーン・モダン」展や「カルティエ、時の結晶」展で300点以上を出展してすごく懲りたのに、今回の「ファッション イン ジャパン」展では結局約820点になってしまいました(笑)。200人以上の出品作家や関係者がいらっしゃるんです。
次にやる時は欲張らず、厳選された形でやろうと思うんですが、自分のなかで毎回新しいチャレンジがしたくなるんですよね。キュレーターとして、これまでなかなか取り上げられなかった作家にフォーカスしたいだとか、あるいは取り上げられてきたけど全然違う見方で見せたいとか。「よくある美術展ね」というような、枠におさまった展示はやりたくないなというのは、常に自分の中にありますね。
学芸員を目指している方や、インターンの応募を考えている方に向けてメッセージをお願いします!
そもそもインターンをやってみようと思う意欲や好奇心は素晴らしいことだと思います。そういったチャレンジ精神と前向きな気持ちを持って、たくさん経験を積むとあたらしい世界がどんどん広がっていくと思います。採用する側も、こんなことをやりましたと聞けば、そんなことができるのなら任せてみようかという気持ちになりますし、いろんな人と出会っていろんな経験をしておくということは、学芸員になるならないにかかわらず、その人をとても豊かにする糧になると思います。
- 【インタビュアー・編集】
- 井口 茉優
2020年度教育普及室インターン生。東京造形大学メディア専攻4年(当時)。
大学ではワークショップ企画などにも携わっている。好きな企画展は「佐藤可士和展」(2021年)

